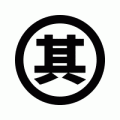目覚ましソフト、「PCアラーム Ver 1.3」を公開しました
【プログラム名】PCアラーム Ver 1.3 【動作確認済みOS】Windows 7/8/10 【必須フレームワーク】.NET Framework 4.5以上 【作者】Trance Cat 【作者サイト】http://www.trance-cat.com/ 【対応言語】日本語、英語、中国語 このソフトが起こしうるいかなる損害も責任を負いかねます。同意の上、ダウンロードしてください。 →→→→→→ダウンロード←←←←←← =Ver 1.3 からの新機能= ・スリープ解除機能。パソコンがスリープ状態に入ってもアラーム発動時刻の一分前にスリープ状態が解除されるように、設定できる。 ・英語UIオプション ・UIをよりわかりやすく ・わかりやすいマニュアル =説明・使用方法・注意= パソコン用の目覚まし・アラームソフトです。 ・フォームが邪魔な時は「フォームを隠す」ボタンで隠してください。隠さずに終了してしまうと、アラームは作動しません。隠されたフォームをもう一度、画面に表示させるにはタスクバー右側の「通知領域」にあるパソコンアラームのアイコンをダブルクリックします。 ・スリープ解除時刻が設定されたままアプリを終了しても、スリープ解除は有効です。スリープ解除をリセットするにはもう一度アプリを起動して「スリープ解除時刻をリセット」をクリックしてください。 ・「次のアラーム時刻の一分前にスリープを解除」をチェックしてアラームを有効にすると、パソコンはアラーム作動時間の一分前にスリープから起きます。なお、これはユーザーがAdministrator(管理者)でないと設定できません。最初はタスクを作成するだけなので設定できる可能性はありますが、のちのタスクの上書き、更新、削除は管理者でないとできない操作なので注意してください。 ・スリープ解除機能はスリープ解除タイマーの許可が有効になっていないと動作しません。スリープ解除機能を使用される場合は必ず以下の設定を行ってください。 =スリープ解除が動作するための必須設定= 1.「コントロールパネル→システムとセキュリティ→(電源オプション)コンピューターがスリープ状態になる時間を変更→詳細な電源設定の変更」まで移動する。 2.「スリープ→スリープ解除タイマーの許可→バッテリ駆動」の設定を「有効」にする。 3.「スリープ→スリープ解除タイマーの許可→電源に接続」の設定を「有効」にする。 これらの設定は管理者権限がないと行えません。 =スリープ解除タスクが登録されているかを確認する方法= Windowsの付属アプリ、「タスクスケジューラ(taskschd.msc)」を実行し、タスクスケジューラライブラリ内に「PC-Alarm」というタスクが登録されているかを確認する。 =言語= このソフトは日本語と英語、両方のデータが組まれています。どの言語を出力するかはシステム環境の言語に基づいているため、日本語以外のシステムをお使いの場合、UIは英語で表示されます。日本語/英語のUIを強制的に表示させるには同胞された「PCAlarm-Japanese.bat(日本語)」もしくは「PCAlarm-English.bat(英語)」を実行してください。 =開発用ソフト= Microsoft Visual Studio 2013 Express =付属アラーム音声= 【トラック名】コーヒーの昼下がり 【トラックURL】http://dova-s.jp/bgm/play051.html 【作曲者】 稿屋 隆 【作者URL】http://dova-s.jp/_contents/author/profile000.html =使用ライブラリ= 【ライブラリ名】Task Scheduler Managed Wrapper 【作者】David Hall 【URL】http://taskscheduler.codeplex.com/ 【ライセンス】MIT License Copyright (c) 2003-2010 David Hall このソフトが起こしうるいかなる損害も責任を負いかねます。同意の上、ダウンロードしてください。 →→→→→→ダウンロード←←←←←←